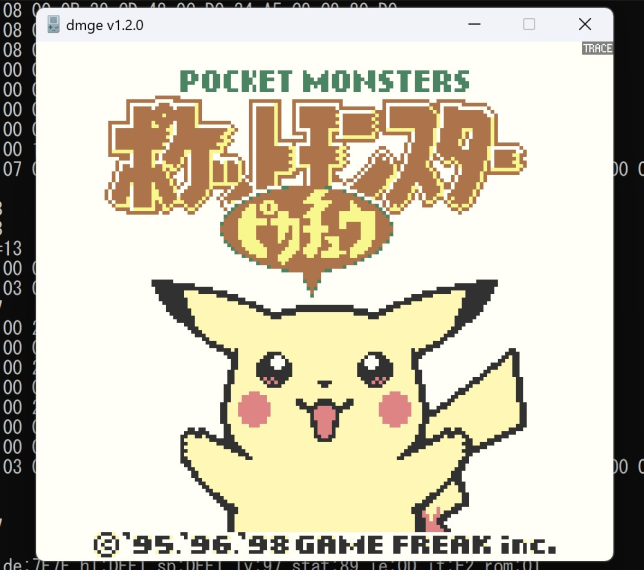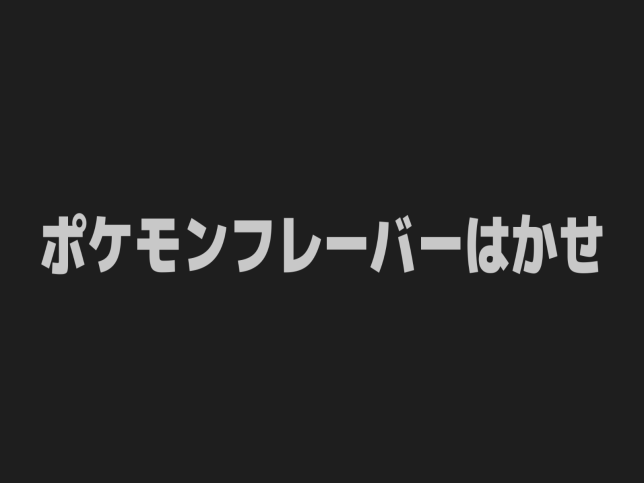10月18日~11月2日に開催された バンダイナムコスタジオ杯 | Siv3D ゲームジャム 2025 に参加してきました。
バンダイナムコスタジオ杯 | Siv3D ゲームジャム 2025 – connpass
このゲームジャムは、 C++ でゲーム等を開発するためのライブラリである Siv3D を使って 2 週間でゲーム制作をするというものです。
前回、第 1 回が 2023 年に開催され、その時の参加者は 70 人くらいでした。今回、最終的に 180 人ほどの参加者となり、Siv3D が盛り上がってきていて何よりです。
なんとか、ある程度の形まで作り上げたうえで提出することができ、ほっとしています。まだ制作の余韻が冷めやらぬうちに、今回の制作過程を思い出しながら記録しておこうと思います。
今回は「Blazing Spiceholics」という、レトロチックな見下ろし型 2D アクションパズルゲームを制作しました。
詳細は、次の作品紹介ページにまとめてあります。提出版のゲームをダウンロードできるので、ぜひ遊んでみてください。5 分くらいでクリアまでいけるかもしれません。
Blazing Spiceholics – バンダイナムコスタジオ杯 | Siv3D ゲームジャム 2025
~~~ 以下、制作記録。ネタバレ要素を含むかも ~~~
続きを読む →